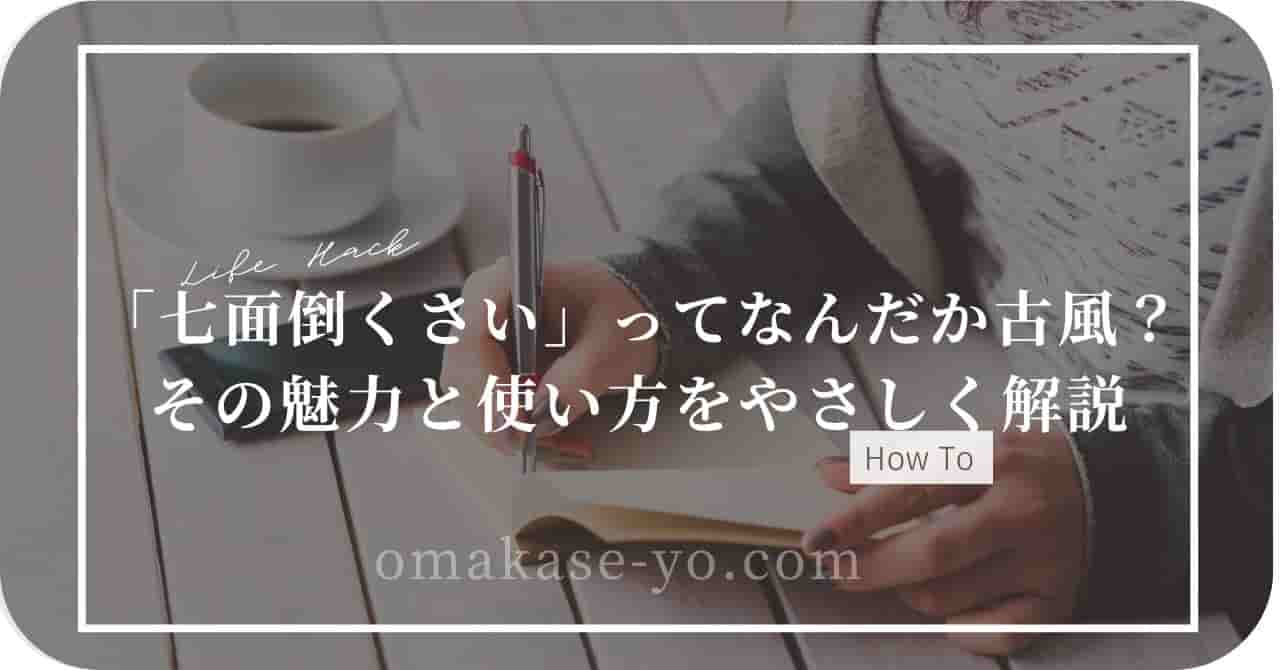「七面倒くさい」(しちめんどうくさい)という言葉、
どこか懐かしさや、
どこかドラマのセリフに出てきそうな響きを感じませんか?
日常生活の中でも耳にする機会があるこの言葉、
改めて意味をじっくり見てみましょう。
七面倒くさいってどんな意味?【まず知りたい基本】
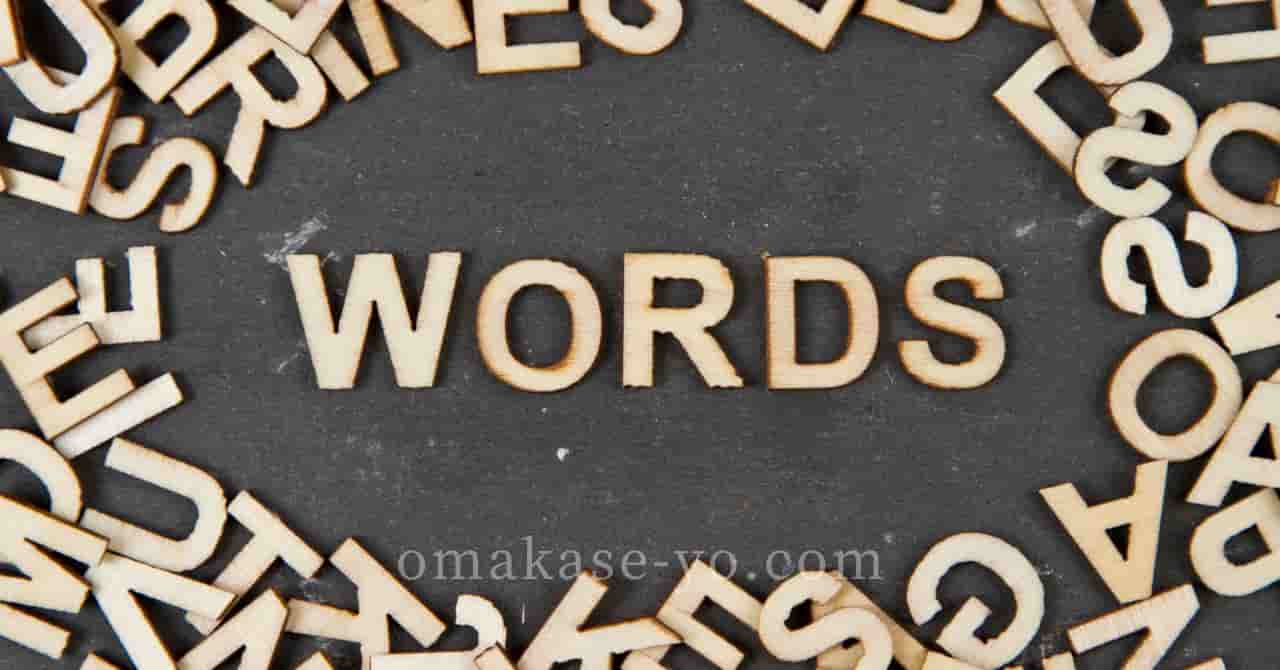
簡単にいうと、
「とても面倒」
「手間がかかってややこしい」
「複雑で煩雑な感じがする」
といった意味合いになります。
ただ単に「面倒くさい」ではなく、その上をいく強調された表現なんです。
- 七(しち):たくさん、数多く(例:七転八起、七難八苦)
- 面倒くさい:手間がかかって気が進まない、煩わしい
つまり、
「七面倒くさい」は
“いくつもの面倒ごとが重なっていて、
どうにも気が重くなる”というようなニュアンスを持っています。
この言葉には、
物事の手間に対するちょっとした苛立ちや、
気乗りしない気持ちが含まれているんですね。
例文でイメージしてみよう
- この手続き、書類が多くて七面倒くさいなぁ。どこに何を書けばいいのか混乱しちゃう。
- 七面倒くさいことは、つい後回しにしちゃって、あとで慌てるのがいつものパターン。
- レシピ通りに調味料を全部揃えるのが七面倒くさいから、だいたいの目分量でやっちゃう派です。
こうして例を挙げると、
「七面倒くさい」がいろんな場面で使える言葉だと分かります。
普段の会話でも、
ちょっとした愚痴やため息交じりのトーンで、
つい口から出るような表現ですよね。
「七面倒くさい」と言うことで、
自分の“気が重い気持ち”や“手間を惜しむ気持ち”を
やんわり伝えることができるのも、この言葉の魅力のひとつです。
なぜ“七”も面倒?ことばの由来と背景をひも解く

「七(しち)」という数字は、
日本語において古くから
「たくさんある」「複数ある」といった意味を込めて使われてきました。
ただの数ではなく、
感覚的に「多さ」を強調する役割を果たすのが特徴です。
たとえば「七難八苦(しちなんはっく)」という言葉は、
多くの困難や苦しみを乗り越えることを指しますし、
「七転八起(しちてんはっき)」は何度転んでも立ち上がるという意味で、
やはり“繰り返し”や“多さ”がキーワードになっています。
同じように、
「七面倒くさい」の「七」も、
ただの数ではなく“面倒がいくつも重なっている”というニュアンスを表していると考えられます。
つまり、「七面倒」=一つひとつの面倒が積み重なって、
気持ちがずっしりと重くなるような状態、というイメージです。
また、
この言葉が生まれた背景には、
昔の生活様式や社会の価値観も影響しているかもしれません。
たとえば、江戸時代や明治時代などには、
今よりもっと手作業や手続きが多く、
それらが煩雑で面倒なものであったため、
こうした「面倒ごとの多さ」を表す言葉が
自然と定着していったのではないでしょうか。
文学にも登場していた?
「七面倒」という言葉は、
実は江戸時代の書物などにも見られる表現です。
当時の人々もまた、
日々の暮らしの中で“面倒がいくつも重なって大変だ…”
という気持ちを抱えていたのかもしれませんね。
古い言葉でありながら、
現代でもなお通じるのは、
それだけ「面倒ごと」への感覚が時代を超えて共通しているということ。
このように、
言葉の背景にはその時代の生活や感情がしっかりと刻まれているんです。
「七面倒くさい」はどこまで通じる?方言・地域差の話

「七面倒くさい」という言葉は、
特定の地域だけで話されている方言ではなく、
基本的には全国どこでも意味が通じる言葉です。
とはいえ、地域によって日常的に使われる頻度や、
その響きに対する印象には少し違いが見られるようです。
たとえば、
関西や九州などでは独自の言い回しや表現が根付いていることもあり、
「七面倒くさい」という表現があまり耳に馴染まない、
という声もあります。
一方で、関東や中部地方などでは、
少し古風ながらも共通語として捉えられている傾向があるようです。
また、世代による使い方の差も興味深いポイントです。
年齢が上の世代では「七面倒くさい」という表現に
馴染みがあり、
文句をやんわり伝える手段として使われることが多いですが、
若い世代の間では少し堅苦しく感じられることもあるようです。
SNSや若者言葉では?
SNSなどのカジュアルな場では、
「しちめんどくさい」という響きが少し“昭和っぽい”“レトロ感がある”と
受け取られることもあります。
そのため、
若い世代はより簡潔で感覚的な表現を使う傾向にあります。
たとえば、
- 「めんどい」
- 「だるい」
- 「タイパ悪い(タイムパフォーマンスが悪い)」
- 「無理ゲー」など
こうした言葉が、
同じような“面倒くささ”を表現するために使われています。
つまり、「七面倒くさい」は現代でも十分通じる表現ではあるものの、
場面や相手、
そして世代によって受け取られ方に差がある言葉とも言えるのです。
そのため、
相手との距離感や状況に応じて使い分けることが大切ですね。
七面倒くさい人ってどんな人?特徴あるある

「七面倒くさい人」と言われると、
なんとなく「一緒にいると疲れそう…」とか「細かくて融通がきかない」というようなマイナスイメージが浮かぶこともあるかもしれません。
でも実際には、そういった人たちの中には、
ものごとを丁寧に進める力や、責任感の強さ、
周囲への気配りが隠れていることも多いんです。
たとえば、日常生活で「七面倒くさい人だなぁ」と感じる相手がいたとしても、よくよく話を聞いてみると、
その人なりの理由や背景があることが分かることも。
表面だけで判断せず、
少し視点を変えてみると、
むしろ信頼できる存在だったりするんですよね。
言われがちな特徴
- 手順やルールにとても厳しい(でもそれは、物事を正確に進めたいという想いから)
- 小さなことでも納得いくまで調べる(妥協せず、本質を理解したい気持ちの表れ)
- 完璧主義で妥協ができない(中途半端な仕事はしたくない、という責任感)
- 時間がかかっても、最後まできちんと仕上げたい
- 他人任せにせず、自分で確認したい気持ちが強い
誤解されやすいけれど…
面倒な人=悪い人、というわけではありません。
「こだわりが強い」と感じる行動の裏には、
「ミスを減らしたい」「誰かの役に立ちたい」「無駄を省きたい」など、
前向きな想いが隠れていることも多いのです。
もちろん、
行きすぎたこだわりが周囲を困らせることもありますが、
そういった時は、お互いにコミュニケーションを取りながら「どこまで丁寧に、どこからは割り切るか」のバランスを探っていけるといいですね。
つまり、「七面倒くさい人」というラベルを貼る前に、
その人の内側にある“真面目さ”や“思いやり”にも、ちょっと目を向けてみたいものです。
現代ではどう聞こえる?印象と注意点
「七面倒くさい」という表現は、聞く人によっては少しきつく、
否定的に感じられることもあるため、使い方には注意が必要です。
特に、相手との距離感や関係性によって、
伝わり方が大きく変わってくるのが特徴です。
たとえば、家族や友人との会話で軽く「七面倒くさい〜」と言えば、
共感や笑いを誘うこともありますが、
職場やフォーマルな場面では「不満を口にしている」と受け取られかねません。
また、目上の人や初対面の相手には、
やや雑な印象を与えてしまうリスクも。
言葉にはトーンや表情といった“空気感”が加わって初めてニュアンスが伝わるものですが、
特にテキストや書面で使う場合は、
相手がどう受け取るかを慎重に考える必要があります。
ビジネスシーンでは避けたほうが無難
ビジネスの現場では、
感情や主観を抑えた言い回しが好まれる傾向があります。
「七面倒くさい」という表現は、
問題に対してネガティブに見える可能性があり、
印象を損なう恐れがあります。
- 「この案件、七面倒くさいですね」→やや失礼に聞こえることも
- 「少し複雑ですね」「工程が多いですね」など、相手や状況に配慮した言い換えが安心です。
- また、「工夫が求められる案件ですね」など前向きな視点を含めた表現も好印象を与えます。
つまり、「七面倒くさい」は感情がにじみ出る言葉だからこそ、
場面を選んで使うことが大切です。
相手に不快感を与えず、
自分の気持ちをうまく伝えるには、
少し言葉を置き換えるだけでも印象がずっと良くなります。
言い換え・類語でやわらかく伝えるには
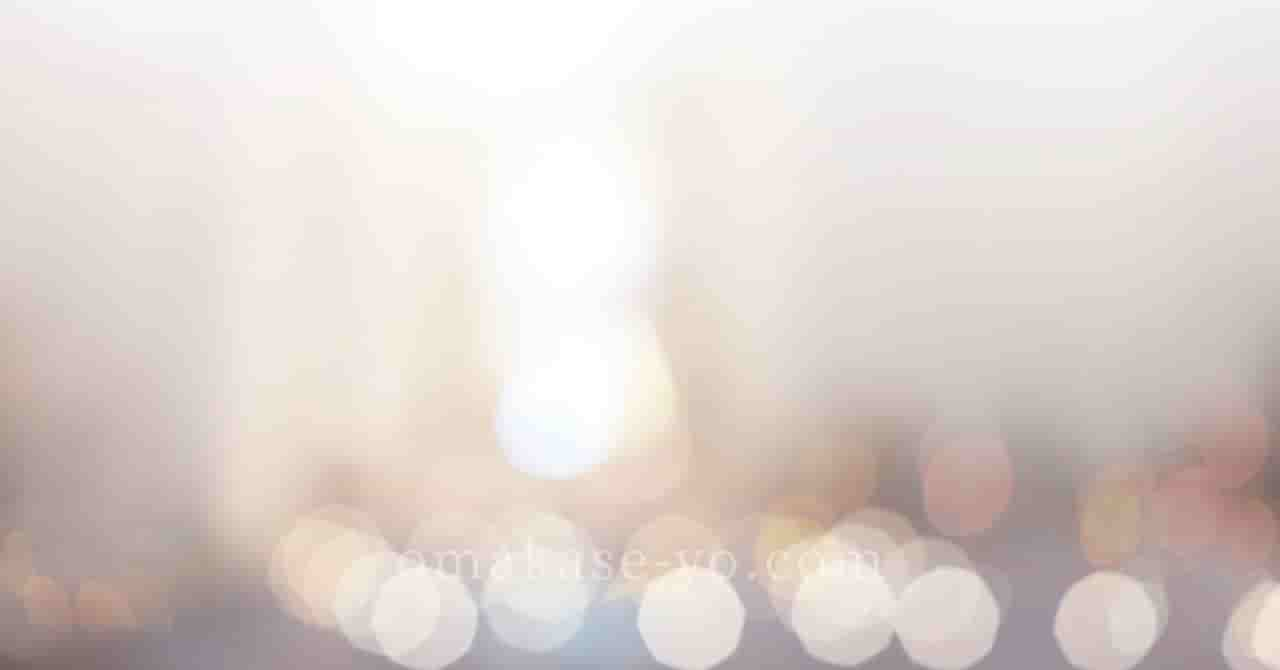
同じ気持ちを伝えるにも、
どんな言葉を使うかで、相手に与える印象はずいぶん変わります。
とくに「面倒」「厄介」といったネガティブな表現は、
状況や相手によっては、きつく聞こえてしまうことも。
そこでおすすめしたいのが、“やわらかい言い換え表現”です。
たとえば、「面倒」という言葉を使いたい場面でも、
言葉を少し変えるだけで、相手への伝わり方がまろやかになります。
特にビジネスシーンや目上の方との会話では、
こうした表現を意識するだけで、印象が大きく変わることもありますよ。
こんな表現に言い換えてみては?
- 面倒 → 手がかかる、大変、手順が多い
- 七面倒くさい → 複雑で少し時間がかかる、工夫が必要な、少し込み入っている
- 厄介 → 手をかける必要がある、丁寧な対応が必要な、気を配る場面が多い
言葉を少し変えるだけで、
「文句を言っている」印象から、
「丁寧に説明してくれている」という印象に変わるのが不思議ですよね。
さらに、口調や語尾をやわらかくするだけでも、
ぐっと伝わりやすくなります。
たとえば「これは七面倒くさいですね」と断言するよりも、
「ちょっと工夫が必要かもしれませんね」と伝える方が、
やさしさや思いやりが感じられます。
ちょっとした工夫で、言葉の伝わり方は優しく、
あたたかいものになります。
ぜひ場面や相手に合わせて、
ふさわしい言い換え表現を意識してみてくださいね。
若者言葉ではどう表す?世代による違いもチェック

若い世代では、
「七面倒くさい」のようなやや長くて重たい響きの言葉よりも、
もっと短くて軽い印象の表現が好まれる傾向にあります。
たとえば、
「めんどい」
「タイパ悪い(タイムパフォーマンスが悪い)」
「だるい」
「しんどい」など、
一言で気持ちを表せるような、
テンポの良い言葉がよく使われています。
こうした言葉は、
スマートフォンの普及やSNS文化とも相性が良く、
文字数を減らしながらも感情を的確に伝えるという目的にぴったりなんです。
たとえば、LINEのメッセージやX(旧Twitter)の投稿では、
「この作業、七面倒くさい…」というよりも
「まじめんどいw」のほうがテンポ感や軽さが伝わりますよね。
また、最近の若者言葉には“共感を誘うフレーズ”が多く、
「それ無理ゲーじゃん」や「詰んだ」なども、
七面倒くさい状況をちょっと面白く表現する形として使われています。
このように、
言葉の選び方にはその時代の空気や、
使う人たちの感覚が強く反映されています。
世代によって同じ意味でも使う言葉が違うのは、
決して“正しい・間違っている”の話ではなく、
「どう伝えるか」「どう受け取られるか」
という言葉の進化を表しているとも言えますね。
英語ではなんて言う?

「七面倒くさい」を英語で言うなら、こんな表現があります。
- It’s such a hassle.
- It’s too much trouble.
- It’s a pain.
ニュアンスを伝えるには、状況に合わせて言い換えるのがコツです。
七面倒くさい!と思った瞬間エピソード

- 保育園の提出書類、毎月チェック項目が変わって七面倒くさい!しかも前月と微妙に違うところがあるのが気づきにくい…。
- アプリの初期設定、パスワードが何度も必要で七面倒くさい…途中でログイン画面に戻されてやり直しになるのがつらい。
- オンラインのアンケート、最初は簡単かと思ったら20問以上あって七面倒くさい…。しかも自由記述が多め。
- 家電の取扱説明書、細かい説明が多すぎて読むだけで七面倒くさい。動画の説明にしてほしいくらい。
- 冷蔵庫の奥にある調味料の賞味期限チェック、ラベルが読みにくくて七面倒くさい…つい放置しがち。
こうして見てみると、
七面倒くさい場面って、日常の中にたくさん潜んでいますよね。
ほんの些細なことでも、
いくつか手間が重なると「もうやりたくない…」という気分になってしまいます。
共感できる“あるある”な体験、
あなたにも思い当たる場面があるのではないでしょうか?
よくある質問(Q&A)

「面倒くさい」と「七面倒くさい」の違いは?
「面倒くさい」という言葉は、
日常でよく使われる表現で、
「ちょっと手間だな」「できれば避けたいな」と感じるような軽い不便さを示す言い方です。
一方で「七面倒くさい」は、
それよりも一段階上の“とても面倒”“何段階にも渡って手間が重なっている”といった強いニュアンスがあります。
たとえば、洗濯物を干すのが「面倒くさい」と感じることはあっても、
洗濯機のエラー解除→排水→脱水やり直し→干す…
という一連の流れにイライラする時は「七面倒くさい!」と表現したくなりますよね。
つまり、「七面倒くさい」は「面倒くさい」の強調形であり、
より深い感情やストレスが込められた言葉なんです。
丁寧に言い換えるには?
少し気になる言い回しを、
やわらかく丁寧に伝えたいときには、
言葉の選び方に気を配ることが大切です。
たとえば、「それ、七面倒くさいですね」と直接言うと、
やや否定的に受け取られることがあります。
そんな時は次のような表現に置き換えてみましょう:
- 「少しややこしいですね」
- 「手順が多いですね」
- 「複雑な手続きが必要なんですね」
- 「工夫が求められそうですね」
こうした表現は、相手に配慮した印象を与えることができるうえ、
自分の気持ちもしっかり伝えられます。
状況に応じて、
柔らかい言葉を選べると会話がよりスムーズになりますよ。
まとめ|「七面倒くさい」は奥深い言葉。使い方を意識すれば、もっと丁寧なコミュニケーションに

「七面倒くさい」という言葉には、
単なる「面倒」という以上の感情や背景がにじんでいます。
いくつもの手間や複雑さが積み重なったとき、
人は思わず「七面倒くさい」と口にしてしまいますよね。
でもその一言の裏には、
「どうしてこんなに大変なんだろう」
「もう少しラクにできないかな」
というような、
小さな戸惑いや、やるせなさ、そして時には“自分なりにがんばっている気持ち”も
含まれていることが多いものです。
そんなふうに考えると、
「七面倒くさい」という言葉を、
ただの愚痴やネガティブな表現として扱うのではなく、
“自分の本音や感情に寄り添うサイン”として
受け止めることもできるかもしれません。
また、相手に向けて使うときは、
その言葉が持つ印象の強さを意識して、
やさしい言い回しに変えてみるだけでも、
コミュニケーションの空気がふっと和らぐはずです。
言葉の選び方ひとつで、伝わり方は大きく変わります。
「七面倒くさい」という言葉を上手に使えば、
相手との距離を縮めたり、自分の気持ちを自然に表現する、
そんな丁寧な対話のきっかけになるかもしれませんね。