手軽にできる絵の具青の作り方
青色の基本知識
青は、寒さや落ち着きを表す色として知られています。
海や空の色として身近で、広がりや自由な雰囲気を感じさせる特徴があります。
青は他の色と混ぜることでさまざまな変化を生み出します。
例えば、赤と混ぜると紫っぽくなり、黄色と混ぜると緑がかった色になります。
また、光には波長があり、青はその中でも短い波長を持っています。
空が青く見えるのは、空気中の小さな粒が青い光を散らすためです。
青は私たちの身近な世界に多く関わり、色のしくみを知る手がかりにもなります。

青の色相環(しきそうかん)における位置
青は色の輪の中で緑と紫の間にあり、寒い色のグループに入ります。
青は、見た目に落ち着きを感じさせる色のひとつで、空や海の色としてもよく知られています。
青の色は、明るさや濃さによっていろいろな種類があり、鮮やかな青から深い藍色、薄い水色までさまざまなバリエーションがあります。
青はいろいろな色と混ぜることで新しい色を作ることができます。
例えば、青と紫を混ぜるとロイヤルブルーに、青と緑を混ぜるとターコイズブルーになります。
デザインや絵を描くときにも、青の持つ落ち着いた印象や信頼できる雰囲気を活かした使い方が多くあります。
青と他の色の混色
青の作り方の基本

三原色を使った青の作り方
食紅を使った青色の作り方
青の絵の具がない場合
青の絵の具がなくても、他の色を混ぜることで青色を作ることができます。
🎨 色を混ぜて作る青のバリエーション
- 水色(シアン)+ 少量の紫 → 深みのある青 🔵💜(鮮やかでしっかりした青色)
- 水色(シアン)+ 少量の黒 → 落ち着いた青 🔵⚫(暗めでシックな印象の青色)
💡 色の特徴と調整のポイント
- シアン(Cyan) は青緑のような鮮やかな色を持つため、そのままでは明るすぎることがあります。
- 紫を少し加えることで 「濃い青」 に、黒を加えることで 「シックなブルー」 に調整可能。
- 混ぜる量を少しずつ調整 することで、理想の青を作りやすくなります!
手持ちの色を組み合わせて、自分だけのオリジナルブルー を作ってみましょう。
濃淡を調整する
青の色合いは、白や黒を混ぜる ことで簡単に調整できます。
明るい青を作るには?
- 青 + 白 → 水色・スカイブルー (やさしく爽やかな印象)
- 白を多めにすると → 透明感のある淡いブルー (軽やかでやわらかい雰囲気)
暗い青を作るには?
- 青 + 少量の黒 → ネイビー・ダークブルー (落ち着いたシックな色合い)
- 黒を加えすぎると → グレー寄りになるので注意!
調整のコツ
- 白や黒は 少しずつ 加えて、理想の色合いになるように調整しましょう!
- ほんの少しの違いで 青の印象がガラッと変わる ので、試し塗りしながら調整するのがポイント
白や黒を活用して、自分好みの 「ちょうどいい青」 を作ってみてください。
身近な材料で作る方法

自然の材料で青を作る
身近な食べ物や植物を使って、青い色を作ることもできます。
たとえば、紫キャベツを煮ると紫色の液体ができます。この液に特定のものを混ぜると、色が変わることがあります。紫キャベツには「アントシアニン」という色素が含まれていて、酸性やアルカリ性の変化によって色が変わる特徴を持っています。
紫キャベツの汁に重曹を加える
紫キャベツを水で煮ると、紫色の液体ができます。この液に重曹(炭酸水素ナトリウム)を加えると、青色に変わります。
これは、重曹がアルカリ性であるため、紫キャベツに含まれる「アントシアニン」という色素が反応して青くなるからです。さらに、少しレモン汁を加えると、液体が赤っぽく変わることもあります。このように、家庭にあるもので色の変化を楽しみながら、青色を作ることができます。
他の自然の材料
ほかにも、バタフライピーという青い花を乾燥させ、お湯に浸すことで青色の液体を作ることができます。バタフライピーティーとしても知られ、お湯の温度やpHによって色が変わる特性を持っています。このように、食品や植物を使って安全に青色を作る方法もあります。
色の作り方の一覧
- シアン + マゼンタ = 青(明るいシアンを多めにするとターコイズブルーに、マゼンタを多めにすると紫寄りの青に変化)
- 青 + 黄色 = 緑(黄色の割合が多いとライムグリーン、青が強いと深みのあるフォレストグリーンになる)
- 青 + 赤 = 紫(鮮やかな赤を混ぜると明るいパープル、深い赤を混ぜると落ち着いたワインレッド系の紫になる)
- 青 + 白 = 水色(白の量を増やすとパステルブルーやスカイブルーへ変化)
- 青 + 黒 = ネイビー(黒の割合を増やすと深いミッドナイトブルーに)
青色の混色のテクニック
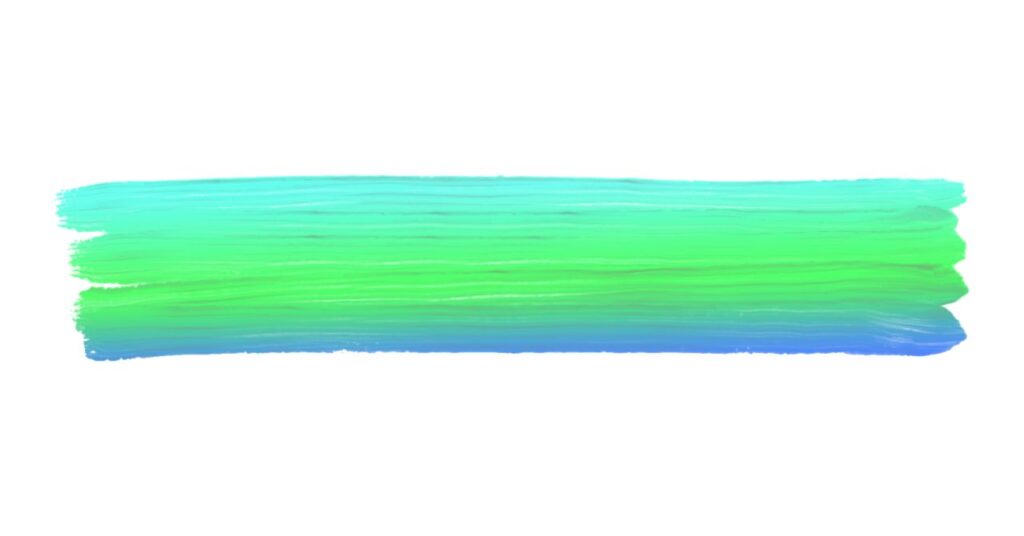
青と緑を混ぜると
青と緑を混ぜると、ターコイズのような色ができます。
この色はエメラルドグリーンに似ていて、海の浅瀬や南の島の水のような明るい色合いです。また、使う緑の種類によっても変わります。
黄色っぽいライムグリーンを混ぜると明るく元気なアクアブルーになり、暗めのフォレストグリーンを混ぜると落ち着いたブルーグリーンになります。さらに、混ぜる割合を少しずつ変えると、色のグラデーションを作ることもできます。
青と緑を組み合わせることで、いろいろな雰囲気の色を作ることができます。
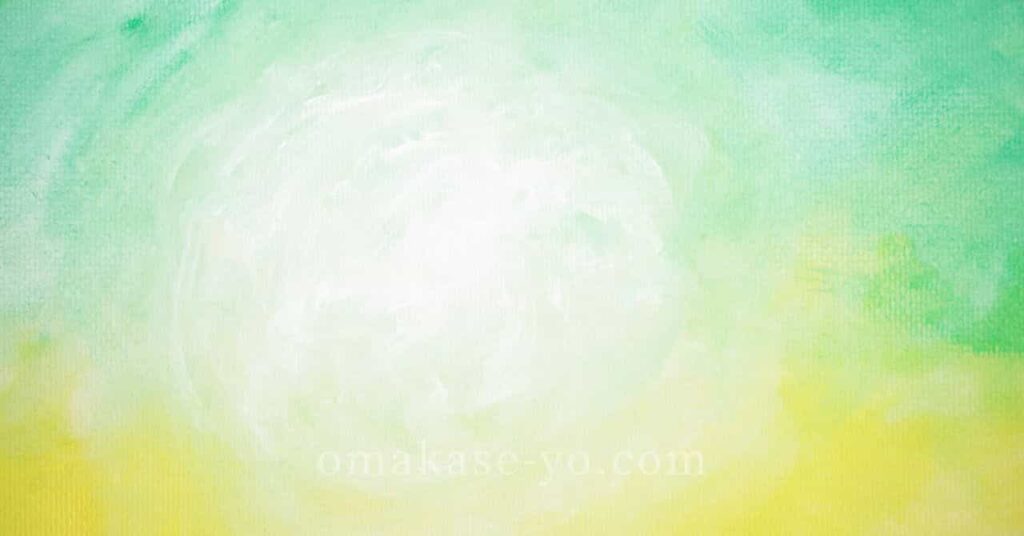
青と黄色を混ぜると
黄の割合が多いほど明るい緑色になります。黄色を多めに加えることで、ライムグリーンやレモングリーンのような爽やかで明るい色合いになります。
逆に、青の割合を増やすと、落ち着いたオリーブグリーンや深みのあるエメラルドグリーンへと変化します。
黄色の種類によっても仕上がりの色合いは異なり、カドミウムイエローを使うと暖かみのあるグリーンに、レモンイエローを使うと涼しげなグリーンになります。さらに、白を加えることでパステル調の優しい色合いになり、黒を加えることで深みのあるシックなグリーンを作り出すことができます。

青と赤を混ぜると
紫系統の色になりますが、赤の種類によって異なる色合いになります。
鮮やかなカドミウムレッドを加えると鮮烈なマゼンタ寄りの紫に、深みのあるバーントシエナを加えると落ち着いたボルドー系の紫になります。
赤の分量が多いと赤紫に近い色合いになり、逆に青の分量が多いと深みのあるロイヤルパープルへと変化します。さらに、少量の白を加えることでパステル調のラベンダーや藤色のような優しい色合いにすることもできます。これらのバリエーションを活用することで、表現の幅を広げることが可能です。
水彩絵の具の作り方
水彩に最適な青色
水彩絵の具では透明感が大事なので、ウルトラマリンやコバルトブルーがよく使われます。
ウルトラマリンは明るくて深みのある青色で、重ね塗りするときれいなグラデーションを作ることができます。
コバルトブルーは落ち着いた色合いで、風景画や人物画に向いています。また、水を多く加えると色が薄くなり、柔らかい表現ができます。
違う種類の青を混ぜることで、自分だけの特別な色を作ることもできるので、いろいろ試してみると楽しいです。
水色の作り方
青に白を加えることで、淡い水色が作れます。
白の量を調整することで、明るく透明感のあるパステルブルーや、やや深みのあるスカイブルーなどのバリエーションを作り出せます。
水を加えることでより柔らかいトーンにすることも可能です。さらに、少量の黄色を加えるとターコイズブルーに、ピンクを加えると可愛らしいラベンダーブルーのような色合いを作ることができます。
水色は空や水を表現する際によく使われる色であり、透明感のある表現に適しています。
シアンと青色の違い
シアンは青に似ていますが、少し緑がかった色をしています。そのため、青よりも冷たくてすっきりした印象を与えます。
シアンは特に印刷やデジタルデザインでよく使われる色で、RGBやCMYKのカラーモデルの基本的な色の一つでもあります。シアンに黄色やマゼンタを混ぜると、さまざまな色を作ることができます。また、光の反射によって、場所や明るさによって見え方が変わる特徴もあります。
絵を描くときにシアンを使うと、深みのあるターコイズやエメラルドグリーンのようなきれいな色を作ることができ、特に海や空の表現にぴったりです。
青色の応用例

絵画における青の使い方
青は、遠近感を出したり、落ち着いた雰囲気を作るのに向いている色です。
寒色系の代表的な色で、空や海の色としてよく使われます。青を背景に使うと、遠くのものがぼんやりとして、奥行きがあるように見えます。
特に、薄い青を使うと軽やかで透明感のある空気を表現でき、濃い青を使うと夜空や影に深みを出すことができます。
灰色や紫を少し混ぜると、落ち着いた雰囲気を作ることができます。このように、青は色のバランスを取るだけでなく、見る人の気持ちや空間の印象にも影響を与える大切な色です。
デザインでの青の効果
信頼感や清潔感を演出するのに最適です。
青は、冷静さや誠実さを象徴する色として、企業ロゴやブランドデザインに頻繁に使用されます。
特に銀行や医療機関など、信頼が求められる業界では青が好まれる傾向があります。
青には知的な印象を与える効果があり、テクノロジー分野の企業や教育機関でも広く採用されています。
青は空や水を連想させるため、清潔感を演出するのにも最適であり、衛生関連の商品パッケージや化粧品にも多用されています。
明度や彩度を調整することで、落ち着いた雰囲気から活発な印象まで幅広く演出できるのも特徴です。
青色のシミュレーション
デジタルツールを使ってさまざまな青のバリエーションを試すことができます。
デジタル環境では、RGBやCMYKのカラーモデルを利用して、わずかな色調の違いを再現することが可能です。
グラフィックソフトウェアでは、スライダーやカラーホイールを使って細かな調整ができるため、理想的な青を簡単に作り出すことができます。
デジタルツールでは光の影響を考慮したシミュレーションも可能で、異なる照明条件下での青の見え方を試すことができます。
レイヤー機能を活用することで、異なる透明度やテクスチャを持つ青を組み合わせ、複雑な色彩表現を行うこともできます。
混色の基礎知識
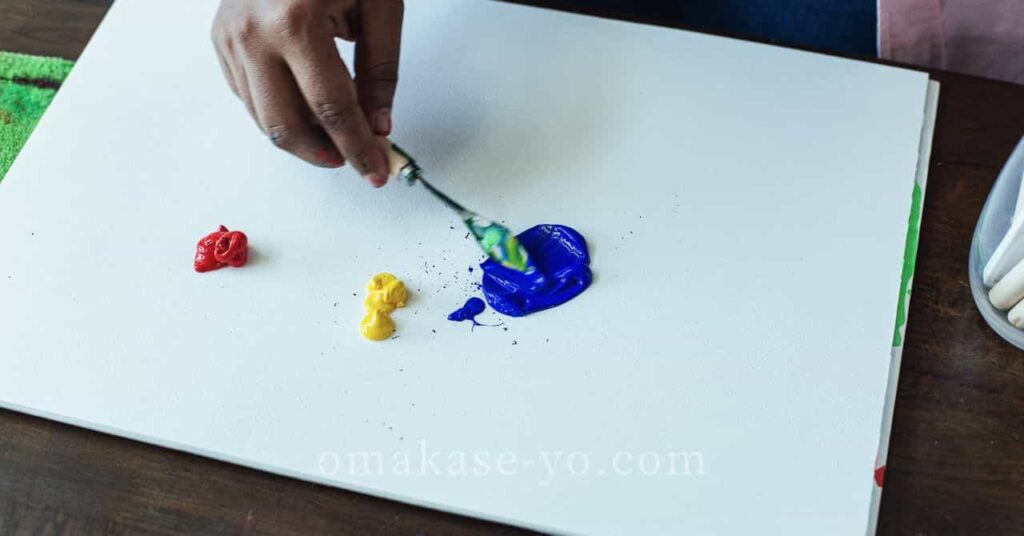
色相環(しきそうかん)を理解する
色を混ぜる際には、色相環の知識が役立ちます。
色相環とは、赤・青・黄の三原色を基に、それらを混色することで生まれる中間色を順番に配置した円形の図です。
これを理解することで、補色関係や類似色の組み合わせを活用し、より魅力的な色彩表現を行うことができます。
色相環の構造を知ることで、色の対比を利用したデザインや絵画のバランスを考える際にも有用です。
色のトーンや明度の調整を加えることで、同じ色でも異なる印象を与えることが可能となります。この知識を活かすことで、意図した効果を引き出しやすくなります。
混ぜる際の注意点
適切な比率や塗り重ねの方法を理解することで、望む色を再現しやすくなります。
例えば、色を混ぜる際には少量ずつ加えて段階的に調整することが重要です。急に多くの色を混ぜると、思いがけず濁った色になってしまうことがあります。
塗り重ねることで透明感を持たせたり、色の深みを出すことが可能ですが、その際には乾燥時間を考慮しながら慎重にレイヤーを重ねることが求められます。
絵の具の種類によっても混色の結果が異なるため、使用する絵の具の特性を理解し、試し塗りをしながら進めることが成功のカギとなります。
色の作り方のセット
基本的な絵の具セットを使い、さまざまな色を作ることが可能です。
絵の具の基本セットには、赤・青・黄の三原色に加え、白や黒が含まれていることが一般的です。これらを組み合わせることで、ほぼ無限のカラーバリエーションを作り出すことができます。
少量の黒を加えることで深みのある色合いにしたり、白を混ぜることでパステル調の柔らかい色を表現することができます。
異なるブランドや種類の絵の具を試すことで、発色や質感の違いを楽しむことができます。水彩、アクリル、油絵の具など、それぞれの特性を活かしながら混色を行うことで、より表現の幅を広げることができます。
色の名前と意味
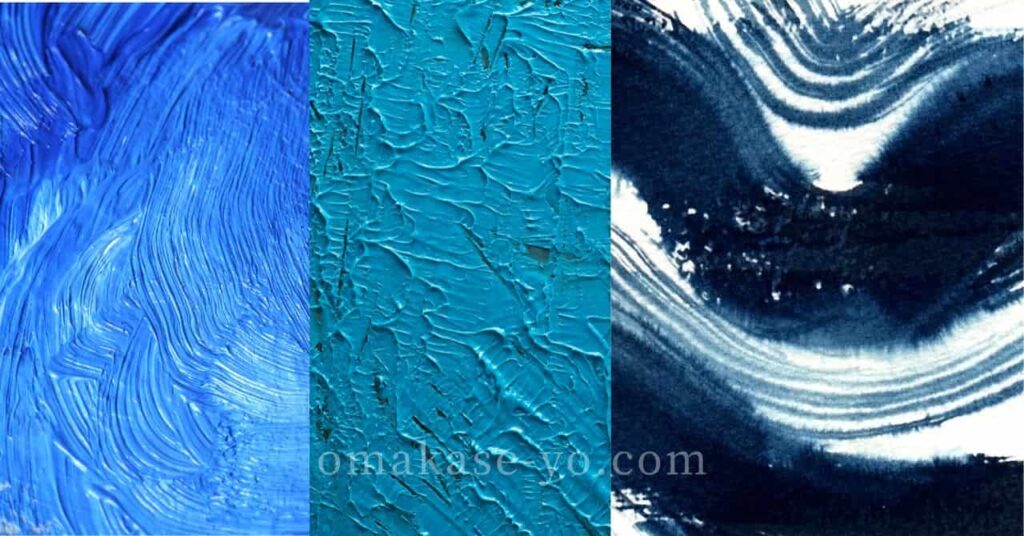
青色のバリエーション
- コバルトブルー:鮮やかでやや紫がかった青色で、発色が良く、特に風景画や空の表現に適しています。また、透明度が高いため、重ね塗りにも適しています。
- セルリアンブルー:明るく爽やかな青色で、特に水や空を描く際に重宝されます。落ち着いた発色と安定した色合いが特徴です。
- インディゴ:深みのある濃い青色で、歴史的に染料としても使われてきました。シックで落ち着いた印象を与え、影の表現や夜景の描写に適しています。
青色に関連する色の説明
青に含まれる成分や色の微妙な違いについて解説します。青色は、顔料や染料によって異なる発色を持ちます。例えば、ウルトラマリンブルーは天然のラピスラズリから作られる鮮やかで深い青であり、合成のウルトラマリンも広く使用されています。
フタロシアニンブルーは非常に安定した青色顔料であり、発色が強く、耐久性にも優れています。セルリアンブルーはコバルト系の顔料を含み、爽やかな空色のような色合いを持っています。
これらの青色は、光の吸収や反射の特性によって微妙な違いが生じ、用途に応じて選ばれます。さらに、青は特定の環境や照明の下で異なる見え方をするため、デザインや美術作品において適切に選択することが重要です。
色の心理的効果
青は冷静さや安定感を与える色とされています。
特に、青は心理的に落ち着きをもたらし、ストレスを軽減する効果があると考えられています。そのため、医療機関やオフィスの壁の色として採用されることが多く、安心感や集中力を高める役割を果たします。
青は知的で信頼感のある印象を与えることから、銀行や企業のロゴにも頻繁に使われています。さらに、青の濃淡によって印象が異なり、明るいスカイブルーは爽やかでリラックスした気分を促し、深いネイビーブルーは高級感やプロフェッショナリズムを強調するのに適しています。
青はさまざまなシーンで人々の感情や行動に影響を与える重要な色の一つです。
混色の具体例
実際の混色プロセス
筆やパレットを使って、色を少しずつ混ぜながら調整する方法を紹介します。
まず、どの色をどれくらい混ぜるかを決め、少しずつ加えて色の変化を見ながら調整しましょう。
最初は薄めの色を作り、だんだん濃い色を足していくと、思い通りの発色にしやすくなります。パレットナイフを使うと、色が均一に混ざりやすくなり、ムラのないなめらかな色を作ることができます。
筆の種類や毛の柔らかさによっても色の付き方が変わるので、いろいろな筆を試してみるのも大切です。
紙に試し塗りをしながら混色を進めることで、思い通りの色ができているかを確認し、少しずつ調整していきましょう。
失敗しない青色の作り方
色を混ぜるときの割合や選び方に気をつけることで、きれいな青を作ることができます。
特に、シアンとマゼンタの量を少しずつ変えることで、明るさや深みの違う青を作ることができます。
白を加えると、明るくてさわやかなスカイブルーになり、黒を少し混ぜると落ち着いたネイビーブルーやダークブルーができます。
いろいろなメーカーの絵の具を試してみると、発色の違いがわかるので、自分の好きな青を見つけやすくなります。
光の当て方や筆の使い方を工夫することで、色の濃さや透明感を変えることができます。このように、色の選び方や組み合わせ方によって、いろいろな雰囲気の青を作ることができるのです。
青と緑の実験
異なる青と緑を混ぜることで、さまざまな色の変化を楽しめます。
鮮やかなシアンブルーとライムグリーンを混ぜると、明るくフレッシュなアクアグリーンが生まれます。
一方で、ウルトラマリンとフォレストグリーンを組み合わせると、落ち着いた深みのあるターコイズブルーが得られます。
混ぜる比率によっても色合いが変化し、青を多めにすればクールな印象のブルーグリーンに、緑を多めにすれば自然なオリーブグリーンのような色合いになります。
白を加えることで柔らかいパステル調の色になり、黒を加えると重厚なダークブルーグリーンに変化します。このように、青と緑の組み合わせは無限のバリエーションを生み出し、風景画やデザインにおいて幅広く活用することができます。
絵の具と混色の楽しみ方

家庭でできる色遊び
家庭にある簡単な材料を使い、色の変化を学べる遊びを紹介します。
水と絵の具を使った混色実験では、異なる割合で色を混ぜることで微妙な違いを観察することができます。
透明な容器に水を入れ、異なる色の食紅を少しずつ加えることで、層になった色のグラデーションを作る遊びも楽しめます。
また、牛乳と洗剤を使った『色の動くアート』では、表面張力の変化により、絵の具が幻想的に動く様子を観察できます。
身近な素材を活用することで、色彩の基本を楽しく学ぶことができます。
子どもと一緒に楽しむ混色
子どもが楽しめる色の実験を紹介します。
食紅や水彩絵の具を使って色を混ぜると、違う色ができることを体験できます。
透明なコップに水を入れ、赤・青・黄色の食紅を少しずつ加えてみると、どのように色が変わるか観察することができます。
シャボン玉液に絵の具を混ぜてカラフルなシャボン玉を作る遊びや、綿棒で紙に小さな点を描き、それを混ぜて色の変化を楽しむアート実験も面白いです。
色水を凍らせて氷の絵の具を作り、それを紙の上で溶かしながら描くと、色がどのように混ざるかを学べます。
これらの遊びは、子どもの想像力を育てるだけでなく、色の仕組みを楽しく学ぶことができるのでおすすめです。
自分だけの青を作る
自分の好きな青色を作る方法を紹介します。
まず、シアンやウルトラマリン、コバルトブルーなど、いろいろな青色の絵の具を試してみましょう。
白を少し混ぜると明るい青になり、水を加えると透明感が出ます。また、赤を少し混ぜると紫っぽい青に、黄色を足すと緑がかった青になります。
メーカーによって絵の具の発色や質感が違うので、いろいろなブランドを試してみるのも楽しいです。最後に、試し塗りをしながら少しずつ調整して、自分の理想の青を作りましょう。


